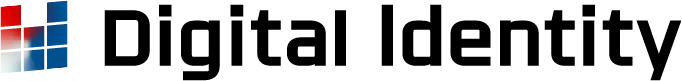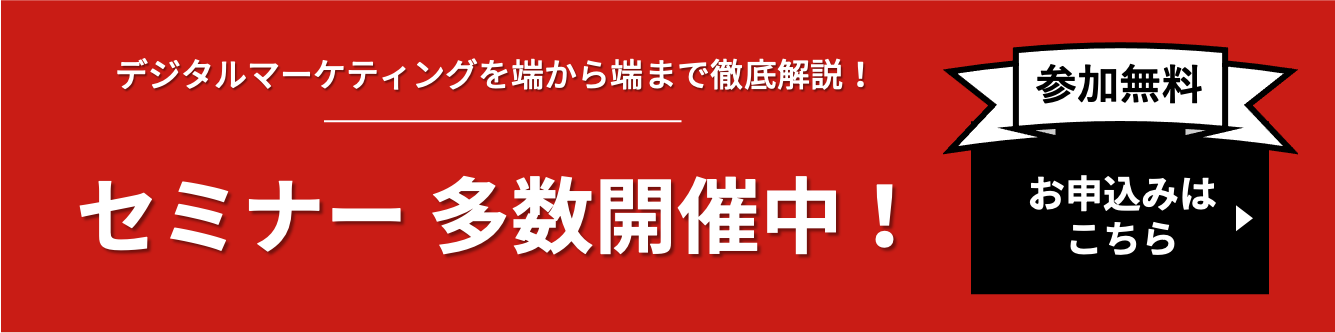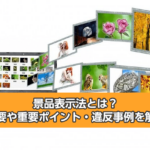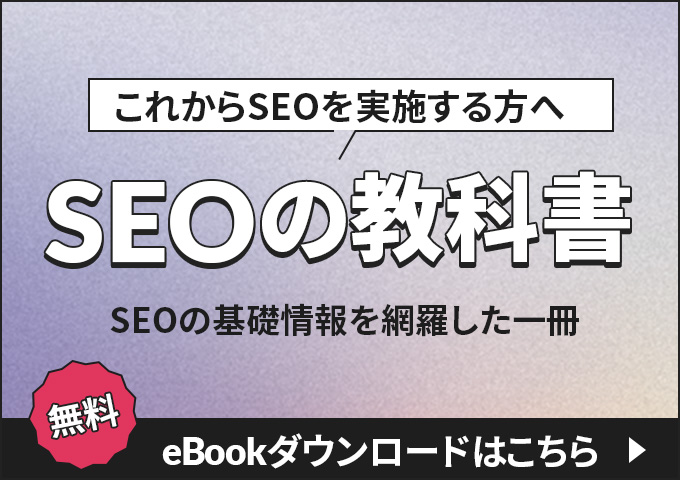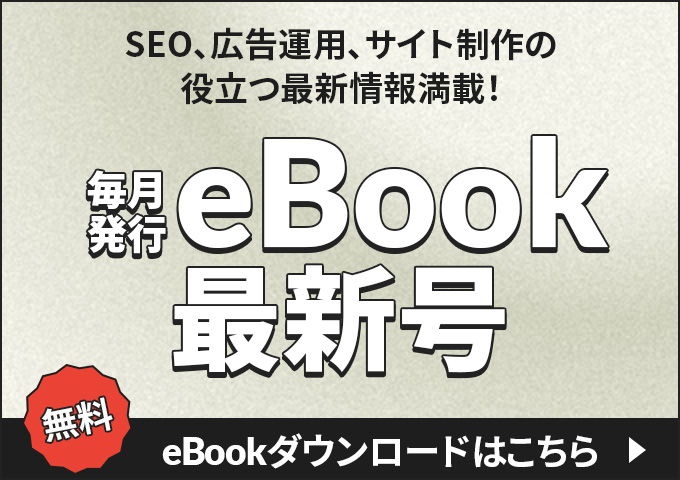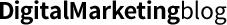- 薬機法
- 更新日:

薬機法は2014年に薬事法から改正され、それ以降より一層表現や表示を厳しく取り締まるようになりました。また、年々細かく変更が加えられている部分があるため、常に最新の情報をキャッチアップしなければなりません。
しかし、中には本質的な業務に注力しなければならないこともあり、薬機法の表現を誤ってしまうケースも多々あります。ただし、表現を誤ってしまうと当然、薬機法違反となってしまい、処罰されてしまう恐れがあることも事実です。
そこで本記事では、薬機法の違反事例を複数ご紹介するとともに、薬機法の違反となる表示例もご説明します。また、薬機法違反とみなされてしまう原因や、薬機法以外に注意するべき法律もまとめましたので、ぜひ今後の参考にしてください。
- 違反の主因は、承認範囲の逸脱や未承認商品での効果効能の標ぼうにあります。
- 「治る」「痩せる」等の断定表現や、不適切なビフォーアフター画像は摘発対象です。
- リスク回避のため、ガイドラインの熟読やツール利用、専門家の監修が推奨されます。
- 薬機法に加え、景品表示法や健康増進法などの関連法規も遵守する必要があります。
薬機法・景表法対応で、安全かつ成果に繋がるコンテンツを。
「薬機法チェックができる人材がいない…」「SEOを踏まえた薬機法対応コンテンツを作りたい…」
そんなお悩みに、500名以上の医師・専門家、1,000名以上の薬機法ライターがご支援します。薬機法管理者の資格を持つコンサルタントも在籍。安全性と成果を両立した施策をご提案します!
目次
薬機法で違反とみなされてしまう原因

それでは薬機法で違反と見なされてしまう場合、一体どのようなことが原因なのでしょうか?
その原因は主に以下の2つです。
- 認められた表記の範囲から逸脱している
- 薬機法の承認を受けていると勘違いしている
それぞれ順番に見ていきましょう。
認められた表記の範囲から逸脱している
薬機法では、ガイドラインにて適正な表示が定められています。加えて、使用してはならない表示も明記されているため、まずはどの範囲までの表示が認められているのかを確認することが重要です。
認められた表記の範囲から逸脱してしまうと、2年以下の懲役、または200万円の罰金、もしくはその両方が課せられてしまうリスクがあります。
さらに、改正薬機法に基づき、2021年8月1日より薬機法に「課徴金制度」が導入されました。これは商品の虚偽や誇大広告を行った者に対して、対象商品の売上から4.5%の課徴金が課せられる制度です。過去3年間を遡って課徴金が課せられます。
薬機法の承認を受けていると勘違いしている
次に、承認を受けていない商品に関して、承認を受けていると勘違いしている原因も考えられます。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関してはもちろん、健康食品等に関しては、表示の許可をもらう必要があります。
許可をいただいていないのに表示をしてしまうと薬機法違反とみなされ、上述した罰金刑や懲役刑が課せられる恐れがあります。
薬機法(旧薬事法)の目的を理解しましょう
薬機法の最大の目的は保健衛生の向上です。 人の健康を保つため、医薬品等の品質や有効性、安全性の確保、危害発生や拡大を予防するための規制をしています。
薬機法の1条にて記載されているので、しっかりと理解しましょう。
第1条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要
ちなみにここでいう再生医療等製品とは、細胞や組織、器官、遺伝子の働きを回復させる再生医療に使われる製品という意味ではありません。
薬機法における定義では、再生医療等製品とは、遺伝子や細胞を使って疾患を治療、予防する製品を指します。
薬機法では医薬品や医療機器に分類できない、遺伝子や細胞を使って治療する製品を再生医療等製品という名前で分類しているんですね。
薬機法における誇大広告等に関する記述
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
薬機法と同じように広告表現を取り締まる法令としては、消費者を誤認させるような不当な広告や、消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供を禁止する景品表示法(景表法)があります。
ただし、景表法が規制する対象は、商品または役務の取引を供給する事業者のみ。
それに対して薬機法の規制対象は「何人も」と定められているのも一つの特徴だといえるでしょう。
景表法については、「薬機法だけじゃない!広告関連で注意するべき法律」で別途解説します。
もし薬機法に違反したらどうなる?気になる罰則の内容

それではもし薬機法に違反してしまった場合、一体どのような罰則があるのでしょうか?
薬機法に違反した場合は、違反者や事業者に対して行政指導が入るのが一般的です。
しかし、その内容が悪質だと判断された場合には、刑事罰として懲役刑、または罰金が課される場合もあります。
また、2021年8月には改正薬機法が施行され、新たに課徴金制度が導入されました。
以前までは、薬機法に違反しても逮捕されない限り罰金は課せられませんでしたが、課徴金制度の導入後は、逮捕されなくても行政の裁量で、違反対象商品の売上に対して4.5%の課徴金が課せられます。
実際の薬機法の違反事例を紹介
薬機法への違反が発覚すると企業としての信用が失われ、違反前のような販売活動を行うことは難しくなってしまいます。
そうならないためにも、今まで実際にあった薬機法の違反事例を知り、間違っても同じ轍を踏まないよう注意しましょう。
「アトピーが治る」…誤解を招く誇大表現
まずは、2013年に薬機法に違反してしまった事例をご紹介します。この事例では、医薬品を使用すると「アトピーが治る」といった表現をしてしまい、無許可で販売したことで結果的に製造販売業の男性が逮捕されてしまいました。
薬機法の表現では、「治る」「安心」「安全」といった言葉はユーザーに誤解を招いたり、誇大表現となってしまったりする可能性があるため、使用は避けるべきです。気づかぬうちに使ってしまうことがないよう、まずはどのような言葉が薬機法に違反するのかを確認しながら表現することが大切です。
「ズタボロだった肝臓が半年で復活…?!」…従業員が逮捕、罰金刑
次に、広告業界に衝撃が走った2020年7月の薬機法違反事件を紹介します。
大阪府警は、「ズタボロだった肝臓が半年で復活…?!」などと肝臓疾患の予防等に関する効果・効能を宣伝した広告が薬機法に違反するとして、健康食品会社の広告担当と広告代理店等の役員ら合わせて男女6名を逮捕しました。
参照:大阪府警、ステラ漢方従業員ら逮捕 ―― 代理店含め「大量摘発」の衝撃
この事件が業界に大きな衝撃を与えたのは、会社の経営陣だけでなく、広告主や製作にかかわった大手広告代理店の従業員までもが逮捕された点にあります。
薬機法はその規制対象について確かに「何人も」と定めていますが、実際にこれが適用されたケースは少なかったため、この事件は改めて薬機法違反の広告に関わると誰でも逮捕されるリスクがあるということを人々に強く認識させる出来事となりました。
さらに、最終的にこの事件では罰金刑までもが課せられています。
コロナに対する効果・効能を謳った商品も次々と摘発
コロナ禍の今、コロナに対する効能・効果を広告で標榜していた薬機法違反事件も続発しています。
2020年に検挙されたコロナに関係する薬機違反事件はなんと14件もありました。
そのうちの一件は、ECサイトのネット広告で「ウイルスが遺伝子の複製の際に必要な必須アミノ酸の産生を阻害し、ウイルスの増殖を抑制する」などとその効果・効能を謳っていたサプリメント。
これはサプリメントの原料であるオリーブ葉抽出物エキスについての学術論文をもとにした広告表示でしたが、サプリ自体は承認を受けていなかったことが判明し、同年3月31日に販売元の健康食品会社とその経営者2人が書類送検されました。
警視庁/新型コロナで薬機法違反/「素材のエビデンスを表示した」
また、同年9月、同じようにコロナに対する効能・効果を標榜したとして、フリーマーケットサイトでビタミン配合のサプリなどを販売していた2人が書類送検されましたが、その売上金額はいずれも数千円~数万円程度だったとのことです。
この事件の裏には「コロナ関連の商品は特に厳しく取り締まる」という警告の意味合いも含まれていると推測されています。
しかし売上金額に関わらず、こういった事態が起こりうることを考えると、やはり薬機法にまつわる広告表現にはどの分野でも注意するに越したことはないでしょう。
そのほか行政指導を受けた薬機法の違反事例
ここまで薬機法違反で逮捕された事例や書類送検された事例を紹介しましたが、そこまではいかなくとも、その他にも薬機法違反によって行政指導を受けた事例は複数あります。ここでは、「清涼飲料水」「主原料が抹茶の飲料水」「主原料が果汁の健康食品」の3つの事例を解説します。
事例①:清涼飲料水
清涼飲料水の事例では「代謝を高め、排出を高める」と謳っていることで行政指導を受けました。代謝や排出を高めることが誇大広告とみなされたことが原因です。
事例②:主原料が抹茶の飲料水
主原料が抹茶の飲料水の事例では「飲むだけで12kgやせ、便秘も解消し、もう二度と太らない体になる」と謳って行政指導を受けました。「飲むだけでやせる」「太らない体になる」などの表現は誇大広告とみなされます。
また、体の機能に影響を与えたり、体の構造が変化したりすることを暗示または明示する表現もNGです。
事例③:主原料が果汁の健康食品
主原料が果汁の健康食品の事例では「食前に飲むだけ毎朝快便肌ツルプル」と表現し、行政指導を受けました。こちらも上述した2つのケースと同様ですが、「〇〇するだけで〇〇」などの表現をしたことが原因です。
上記3つに共通して学ばなければならないことは、「誇大広告をしないこと、体が変化することを暗示・明示しないこと」です。また、上記の3つは飲料水や食品であり、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の承認を受けているわけではないため、あくまで飲料水や食品であることを理解して表現することが重要です。
薬機法違反になりかねない!注意が必要な表示例

薬機法の違反事例は複数ありますが、そのどれもが似たような表示をしていることで違反とみなされるケースが多いです。特に、下記4つの表示例には注意が必要です。
- 健康食品
- 薬用化粧品
- 第三者の口コミ
- 打ち消し表現
それぞれの違反となる表示例を順番にご説明します。
健康食品
健康食品では、健康食品の効果を表記する必要があります。ただし、表現を誤ってしまったり、事実と異なる表現をしたりしてしまうと、「誇大広告」とみなされてしまうため注意が必要です。
- 「〇〇を飲むだけで痩せる」
- 「〇〇によって血圧が下がる」
たとえば、上記2つは誇大広告とみなされる可能性が高いです。「〇〇を飲むだけでやせる」という表現は体の変化を明示しており、「〇〇によって血圧が下がる」は医薬品のような表現となっています。
また、摂取方法・調理方法・摂取量の上限を示す場合は良いのですが、その他の用法や容量を示すことはNGとされています。
化粧品
リップ、ファンデーションなどのコスメや、シャンプー・リンスなどのヘアケア商品、化粧水、美容液などのスキンケア商品。こうした化粧品にも薬機法が適用されます。
薬機法第2条3項では、化粧品について次のように定義しています。
“この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。”
法律上で化粧品は「容姿を魅力的に見せるもの」と定義されているため、この範囲を超えた表現はできません。
例えば、「○○シャンプーならフケが“治る”」「××コンディショナーで“傷んだ髪を回復”」など、効果・効能を謳う表現はNGになります。
一方で、次のような表現は承認されています。
- フケ、カユミがとれる、フケ、カユミを抑える
- しなやかな質感に、クシどおりをよくする
また、化粧品の中には医薬部外品(薬用化粧品)に該当する商品もあり、こちらは「予防」「防止」などの効果・効能を書くことが可能です。
第三者の口コミ
SEOコンテンツやLP(ランディングページ)等で、第三者の口コミを扱うケースは多々あるでしょう。個人の感想程度で留める分には問題ないのですが、下記のような表現は誇大広告とみなされてしまう可能性があります。
- 絶対に効果あり
- 実際に効果がありました
- 病気が治る
このように、確実に何らかの効果があることを示したり、病気が治るといった表現をしたりするのはNGです。口コミをコンテンツに取り入れる場合には、必ず「個人の感想です」といった表現や、会話調・疑問形を使用するなどして、確実に効果があることは謳わないようにしましょう。
打ち消し表現
薬機法を意識するあまり、やってしまいがちなのが断定を避ける「打ち消し表現」です。
例えば次のような表現をよく目にします。
- 効果・効能を表すものではありません
- あくまで個人の感想です
このような表現は、効果・効能を強調しながらも断定を避けることで、薬機法違反を回避しようと用いられます。
しかし、打ち消し表現を使っても効果・効能を書いているという事実が見逃されるわけではありません。
薬機法違反として処罰されるリスクがあるため、打ち消し表現の使用を前提とした書き方には充分にご注意ください。
画像が薬機法違反になることも

美容系の広告では、ダイエット前とダイエット後の姿を比較するようなビフォーアフターの画像がよく使われています。
実はこのビフォーアフターの画像が、薬機法に抵触する恐れがあることをご存じでしょうか?
元々ビフォーアフター画像は、使用自体が認められていませんでした。
しかし、2017年に行われた医薬品等適正広告基準の改正により、条件を満たしている場合に限り、使用が認められています。
では、どのような条件が定められているのでしょうか?
現在の広告基準では、次に該当する画像は使用できません。
- 承認されている範囲以上の効果・効能があると思わせる
- 効果が現れるまでの時間を保証している
- 効果の持続時間を保証している
- 安全性を保証している
つまり、承認されている範囲を逸脱しないのであれば、効果が現れるまでの時間、持続時間、安全性などを保証しない限り、ビフォーアフター画像の使用が認められます。
ただし、別人を同一人物のように見せたビフォーアフター画像は、効能効果の保証となってしまうことからNGです。
“良い印象のイラストと悪い印象のイラストを並べて記載することや、異なる部位の写真で印象が良いものと悪いものを並べて記載することで製品による効果と結びつけて受け取られることを企図したものは、それが、使用前後の写真等の表現であるかどうかを問わず、医薬品等適正広告基準第4の3(5)に抵触すると判断される場合には、指導対象とすべきと解する。”
薬機法で違反しないために今できること
薬機法は、知見のある方でも、どこまで表現をして良いか悩むほど難しい法律です。ここからは、薬機法に違反しないために今できる3つのことをご説明します。
- ガイドラインを必ず確認する
- 薬機法チェックツールを利用する
- 専門家の監修を入れる
それぞれ順番に見ていきましょう
ガイドラインを必ず確認する
まずは、必ず薬機法のガイドラインを確認しましょう。量は多いですが、厚生労働省が出している薬機法に関する資料の一部を下記に掲載します。
「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン」について
これらをすべて確認する必要はありませんが、最低限「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器」の4つに関しては理解を深めましょう。薬機法は注意しなければならないポイントが非常に多いように感じるかもしれませんが、一度ポイントを抑えてしまえば、改正があったとしてもさほど大きな違いは生まれません。
薬機法チェックツールを利用する
次に、薬機法チェックツールを利用しましょう。薬機法チェックツールは複数ありますが、下記3つのツールがおすすめです。
薬事法 広告表現チェックツール:完全無料で利用できるツール。主に、健康食品に関連する薬機法に抵触していないかを確認できます
KONOHA:コスメ、健康食品に関連する広告・文章が、薬機法や景品表示法に抵触していないかを確認できるツール
Cosme Design:化粧品の薬事表現チェックツール
これら3つのツールを、自社のプロダクトやサービスに合わせて利用しましょう。しかし、ツールのみの確認では不安に感じる方も多いでしょう。そういった場合は、次で解説する「専門家の監修を入れる」ことを推奨します。
専門家の監修を入れる
薬機法の専門家の監修を入れることで、Webサイトや広告に関連する表記をくまなく確認できます。加えて、ユーザー目線から見ても信頼性の証拠となるため、商品の権威性を高められることにも繋がるでしょう。
弊社デジタルアイデンティティでも、薬機法コンテンツマーケティングサービスをご提供しています。医師・薬剤師の監修のもと、医療・美容・通販業界に特化したコンテンツSEOをご提供できますので、薬機法を守りながら新しい販路を開拓したい企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。
薬機法だけじゃない!広告関連で注意するべき法律

注意しなければならないのは薬機法だけではありません。
広告を扱うのであれば、薬機法以外に次の3つの法律に注意が必要です。
- 景品表示法
- 健康増進法
- 不正競争防止法
それぞれどんな法律なのか?以下で解説していきます。
景品表示法
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、不当な表現や景品から一般消費者を守るために存在する法律です。
景表法では、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽ることがないよう、表現に制限を設けています。
同時に、過大な景品の提供で消費者の選択を迷わせることがないよう、景品類の最高額も決められています。
“景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。”
引用:景品表示法
景表法に関して、広告で注意するべきは「優良誤認表示」「有利誤認表示」の2つです。
| 優良誤認表示 | 商品やサービスの品質をはじめとした内容について、事実と異なり他社より著しく優れていると誤認される表示 |
|---|---|
| 有利誤認表示 | 商品やサービスの価格をはじめとした取引条件について、事実と異なり他社より著しく優れていると誤認される表示 |
例えば、健康食品が何の根拠もなしに「世界一売れている!」などと表現することは、他社よりも商品が著しく品質が優れているように偽っていることから、「優良誤認表示」に該当します。
ただし、明確な根拠があればこの限りではありません。
また、存在しない競合他社と比べて「弊社の商品はこれだけ安い」と安さを強調するのは「有利誤認表示」に該当し、こちらもNGです。
健康増進法
健康増進法第65条第1項には、次のような規定があります。
“何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。”
引用:誇大表示の禁止
簡単に言うと、ある食品について、実証されていない効果・効能を期待させる表現をしてはならないということです。
例えば糖尿病や高血圧など、具体的な病名を出して「治る」「予防できる」などと表示するのはもちろん、よくある「疲労回復」「免疫機能の向上」「おなかの調子を整える」などの表示も、問題となる可能性があります。
健康増進法の難しいところは、誇大表示に該当するか否かの判断について、一般消費者が受ける印象が基準になっているという点です。このため、ある表現が一概にダメと言われるのではなく、内容全体から違反かどうか判断されます。
他にも、誇張の程度が許容の範囲を超えている表示や、事実と違いがある表示、人に誤った印象を与える表示などは、健康増進法違反に問われるリスクがあります。
不正競争防止法
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を実現するための法律であり、広告表現にも規制が定められています。
不正競争防止法で注意するべきは「混同惹起行為」「著名表示冒用行為」「誤認惹起行為」の3つです。
| 混同惹起行為 | 一部消費者の間で知られている商品や屋号と同一、または類似のものを広告内で使用する |
|---|---|
| 著名表示冒用行為 | 全国的に知られている商品や屋号と同一、または類似のものを広告内で使用する |
| 誤認惹起行為 | 消費者に誤認される表現を使用する |
混同惹起行為と著名表示冒用行為は似ていますが、どちらも「既存の商品や屋号に似たものを広告内で使用しない」という点は同じです。
両者の違いは目的で、混同惹起行為は、消費者が商品や企業を混同する事態を防ぐために定められています。
一方で著名表示冒用行為は、消費者の混同を防ぐことに加え、ブランドイメージへ悪影響が及ぶことや、集客力を不当に利用することを防止する目的でも規制されています。
誤認惹起行為について、規制されるのは以下の項目です。
商品の場合:原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量
サービスの場合:質、内容、用途、数量
“この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
(中略)
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為”
まとめ

薬機法の違反事例や、違反しないために今できることを解説しました。薬機法は懲役刑こそ事例として少ないものの、行政指導を受けているケースは多々あります。本記事を読む方も、知らぬうちに万が一の可能性として薬機法に抵触してしまう可能性がないわけではありません。
だからこそ、まずは薬機法のガイドラインをしっかりと読み込み、ときには専門家の監修を入れるなどして、ユーザーに安心してサービスを届けられる工夫をしましょう。
薬機法・景表法等の広告表現にお悩みの方へ
株式会社デジタルアイデンティティでは、専門性の高い薬機法・景表法に対応するソリューションを提供しています。
アサインできる医師・専門家は500名以上、薬機法ライター1,000名以上!
お客さまの業界・商材にマッチした人材で、安全性に考慮したより魅力的な商品訴求・コンテンツを実現します!
こんな方におすすめ!
- 薬機法チェックのリソースがない / 人材がいない…
- 薬機法に準拠した高品質な記事を作成したい…
- 薬機法に関する記事作成を丸投げしたい…
- 薬機法だけでなく、SEOも踏まえた記事作成がしたい…
- 医師や専門家に監修を依頼しらい…
- 新しい施策にチャレンジしたい…
また、SEOや広告と連携した施策の提案から実行までワンストップで対応可能。
コンテンツの安全性だけでなく、成果にコミットしたご提案をいたします!